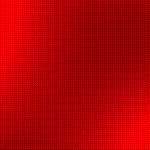アニメスタジオクロニクル Vol.22 東映アニメーション 森下孝三
アニメ制作会社の社長やスタッフに、自社の歴史やこれまで手がけてきた作品について語ってもらう連載「アニメスタジオクロニクル」。多くの制作会社がひしめく現在のアニメ業界で、各社がどんな意図のもとで誕生し、いかにして独自性を磨いてきたのか。会社を代表する人物に、自身の経験とともに社の歴史を振り返ってもらうことで、各社の個性や強み、特色などに迫る。
第22回には、現存する日本のアニメ製作会社で最も古くからの歴史を持つ東映アニメーションの代表取締役会長・森下孝三氏が登場。1948年生まれ、1970年に当時の東映動画に入社した森下氏は、東映グループ全社員の中でも“最古参”であるという。そんな森下氏が語る東映アニメーションのターニングポイントは、日本の商業アニメーションそのもののターニングポイントと言えるものだった。
取材・文 / はるのおと 撮影 / ヨシダヤスシ
戦後10年ほどで商業ベースのアニメ制作を始めて
「太平洋戦争が終わったのが1945年。驚くことに、日本が焼け野原になってから10年ほど経った1955年頃にはもう、商業アニメを作ろうという動きがあったんだよね。アニメーション的なものは日本はもちろんいろいろな国に存在したけど、いずれも小規模な存在で、その頃に商業ベースでアニメを製作する大規模な会社を作ろうと決断した東映の大川博さんはすごいですよ」
東映アニメーションの創立時について聞いたところ、森下氏はまず、戦後復興の最中で同社の創立に深く関わった東映の故・大川博社長への深い敬意を示した。大川氏は、1948年に設立された小規模なアニメ製作会社・日動映画の買収を決定した人物だ。これが現在まで続く、“東映”の名を冠したアニメスタジオの始まりとなる。
「1ドル360円という円安の当時、マルチプレーンカメラなどアニメ製作用の機材をかなりの予算を組んでアメリカから輸入してきて、『東洋のディズニーを目指すんだ』って言ってたそうで。今、大川さんが生きてりゃ、『なぜそこまでしてアニメをやろうとしたの?』って聞いてみたい(笑)。彼に関する本なんかによると『アニメで世界に出てドルを稼ぐ』という思惑はあったようだけどね」
1956年の買収時に日動映画は東映動画へと社名を変更し、処女作「こねこのらくがき」や日本初の長編カラーアニメ映画 として名高い「白蛇伝」を皮切りに、多くの作品を世に送り出していく。東映アニメーションという現在の社名となったのは、東映動画創立から40年以上経った1998年のことだ。
「僕も1980年頃から何度か海外を視察したけど、アニメーションを指す日本語の『動画』という言葉は全然通じなかった。だから海外でも意味が通りやすい東映アニメーションという社名に変更することになったんだよ。もちろん、長く会社にいる人には東映動画という名前に愛着を持っている人たちもいた。でも世界に展開するという点では東映アニメーションという社名のほうがいいよね」
生き証人が振り返るTVアニメ黎明期
森下氏は、1970年に東映動画に入社した。それからさまざまなポジションでアニメに関わりながら50年以上務め続け、今では東映グループ全体でも最古参。「54歳くらいからずーっと病気だったけど、よく雇ってくれているよね」と笑う。会社の、そしてアニメ業界の生き証人とも言える彼に、入社時のアニメを巡る状況を振り返ってもらった。
「1964年の東京オリンピックが開催される前後にカラーテレビが爆発的に普及したでしょ。それに伴ってテレビ局も増える中で、郵政省(現在の総務省)から新設の民放に対して『教育番組を一定の割合で流すように』といった指示があって、その時間にアニメを流そうという機運が生まれたんです。ただ、それまでテレビで流れていたのは「ポパイ」とかアメリカのアニメばかりだった。まあ当時はアニメだけでなく、ドラマとかもアメリカやヨーロッパのものが多かったけど。その中でアニメは『お金をかけてアメリカから仕入れるより、自分たちで作ったほうがいいんじゃないか』とみんな考えて、だんだんと国産が増えていきました。
そんなふうにTVアニメの需要が急激に高まったおかげで、アニメ業界は人手が全然足りなかった。一方で「白蛇伝」以降の10年とかで映画はどんどん衰退していたので、人手が映画からテレビに流れてきたんです。うちはもともと映画会社のグループだったのもあるけど、そういった歴史があったから、今も映画とほぼ同じような工程で、撮影や仕上げまで全部社内で完結できるような規模でアニメを作っています。東映動画の後にもアニメを作る会社はたくさん出てきていたけど、当時ここまでの規模の会社をいきなり作るのは資本的に難しかったでしょうね」
演出と企画、2つの側面から東映アニメに関わり続けて
1970年の入社後、森下氏は作品製作に演出と企画の両面で関わることになる。入社当初から1988年までの演出時代と、それ以降を振り返ってもらった。
「最初は演出助手として働き始めました。ほかの会社で言う助監督。うちの場合は映画製作を踏襲しているから助手って呼ぶんだけど、助手を5年とかやっても仕方ないんですよ。演出助手のプロなんて会社には求められないわけで。そこから演出になれなきゃ、演出としては振り落とされるだけだし。だから、演出助手を2年か2年半くらいやって初めて助手のない“演出”として手がけた『キューティーハニー』は思い出深いなあ。
それから39歳くらいまでシリーズディレクター(※他スタジオにおける監督)なんかをやっていて、その頃の『聖闘士星矢』とかは特に一番力を入れていたけど、そのへんで『いつまでもディレクターは続けられないな』と感じていて。新しい人がどんどん入ってくる中で彼らにもシリーズディレクターを任せなきゃいけない。でも自分が今さらローテーション演出(各話演出)をやるのも違うなと。50歳や60歳で演出をしている人もいるけど、自分は同じことをやり続けるとワンパターンになるだろうし、枯れちゃうのが嫌だった。
そんなふうに思っているときに会社から『企画部に来てほしい』という話があって、企画(※他スタジオにおけるプロデュース)側に回りました。と言ってもプロデューサーとしては『ドラゴンボール』しかやってないようなもんだけどね。あとは自分の趣味みたいな映画をやったくらいです」
それから2000年前半にいたるまで、森下氏は企画部でアニメ製作に関わり続けた。その30年以上のキャリアの中で出会った才能あるクリエイターについて、彼は具体的な名前を挙げて語る。
「アニメーターで言うとまずは荒木伸吾さん。あとオールマイティだった小松原一男さんと、発想力が豊かな湖川友謙さん。この3人はすごかったですね。ずいぶん勉強になりました。特にTVアニメの第1話やオープニングはそういった最高のスタッフで作るから、すごく勉強になるんです。もう、授業料をいくら払っても足りないくらい。
今でもいろんなプロデューサーに言うけど、結局そういったうまい人とやらなければ自分が成長しないんですよ。単にフィルムがつながったからって完成じゃない。自分が下手でも、本当に自分がやりたいことを見極めて、それに合った上手な人とやってフィルムの内容を引き上げてもらわないと」
「マジンガーZ」で会社の経営状況、業界の展開が一変
長年アニメに関わり続けるだけに、本連載における恒例の質問「御社のターニングポイントになった作品は?」に対する回答には頭をひねらせるかと予想されたが、森下氏は瞬時に、ある作品の名を挙げた。1972年に放送が始まり、ロボットアニメの金字塔として今も語られる「マジンガーZ」だ。
「ターニングポイントは完全に『マジンガーZ』です。と言っても『マジンガーZ』という作品というより、この番組でバンダイさんと組んだこと。『マジンガーZ』からはロイヤリティが、グッズが1個売れたらいくらというロット型になったんだけど、これはバンダイにも同じ考えの人がいたからできたんです。それまでは、例えば製菓会社に300万でお菓子にする権利を渡したりしていたけど、なかなか商売にならなかったし、おかげでずっと赤字だった。だけど『マジンガーZ』のやり方で経営がものすごく安定したし、その後も同様の版権商売がうまくいったんです。
あと『マジンガーZ』の何が画期的だったかって、テレビで放送されてすぐに、おもちゃ屋さんに行けばマジンガーZの超合金のおもちゃがあり、スーパーに行けばマジンガーZのお菓子があること。このスピード感はそれまで考えられなかった。アニメが当たるかどうかわからなくて、先に商品を作っておくのはリスクがあるから。
当たるかどうかわからない『マジンガーZ』で、永井豪さんとうちとバンダイさんがリスクを背負ってそういうシステムを作り上げたのはすごいと思う。今では放送されたタイミングでグッズを展開しているなんて当たり前の光景だけどね」
ライブラリーの膨大さこそ、東映アニメーションの最大の強み
東映アニメーションは、初のTVアニメである「狼少年ケン」をはじめとして、「マジンガーZ」はもちろんのこと、多くの映像作品の著作権を所有している。それを活用した版権ビジネスを最大化するのがライブラリーの豊富さだ。森下氏は、これこそが東映アニメーションにとって最大の強みだと強調する。
「東映アニメーションはテレビ作品の著作権を基本的に持っているんだよね。原作ものは原作著作というのが別枠であるけど、フィルムに関する著作権は100%保有する。だからグッズなどのライセンスビジネスや海外展開なども全部自社でやれて、ビジネスとして成り立っている。
例えば『一休さん』なんて7年間で350本ぐらい作ったけど、1社提供で製作費はすごく安かったから、作れば作るほど赤字だったの。でも最近、中国などですごい人気になって、製作費はほぼ回収できちゃった。そんなふうに今までの作品の90%は製作費を回収してるんじゃないかな。だから、もし作った時点でビジネス的に失敗しても、ライブラリーという資産を増やすことにつながっていればいいんです。
しかもうちは年間約50話の作品を5ラインで作っているから、1年で約250話分作る。これだけ資本を投下して、膨大なライブラリーを蓄積できていると言えるのは、うちと日本アニメーションとサンライズくらいじゃないですか。そういう大きな屋台骨があるのはすごくいいこと。そのおかげでチャレンジができる。入社してからずっと『ドラゴンボール』だけ描いています、あるいは『プリキュア』だけ演出していますという人が、『違う作品をやってみたい』と思ったときにも、別のチャンスを与えられるんです。そのチャレンジこそ社員のモチベーションになる。もちろんそうしてできた作品が確実に儲かるわけではないから、ビジネスとして考えるとリスキーではある。でもそういった作品だってライブラリーの1つにはなる」
過去のライブラリーという資産を活かした余裕があるためか、同社は今では当たり前となっている海外展開やデジタル技術の導入を早くから行っていた。後者に関しては1980年3月と、45年以上前にコンピューターによるアニメ製作の本格的な研究を開始したという。
「当社に研究開発室ができた頃は大型コンピューターしかない時代だから、机上の話が中心だったようだけど、そのうちゲーム開発なんかにも手を出していったんだよね。『北斗の拳』とかアニメを原作としたものを10本出してすごく売れたけど、オリジナルIPを出したらコケちゃったね(笑)。90年代からコンピューターの性能が上がったこともあり、アニメ製作のデジタル化が進み、『狼少年ケン』を白黒からカラーにする実験映像を製作したよ。コンピューターで1コマずつ色を塗ってカラーになったことはなったけど、ものすごい金がかかった(笑)。でも、それが研究でしょ。今だとAIとかも同じように研究しているけど。」
どんな作品にもある“面白い”部分を活かした展開を
「失敗した作品もライブラリーの1つにはなる」と語る森下氏にも、悔いが残る作品があるという。ジョージ秋山によるマンガを原作として、2012年にフルCGでアニメ化した映画「アシュラ」だ。同作に森下氏は企画・監修のほか絵コンテとしても参加していた。
「『アシュラ』は実はすごい低コストで作っててさ。それでもクオリティは高くて技術面を評価されて賞こそもらったけど(編集部注:第16回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞を受賞)、興行的にはコケてしまって。でも長い目で見れば、1作で終わりにするんじゃなくて何本か続けていけるようなIPとして扱わなきゃいけなかった。オリジナル作品でも、1作で終えちゃうと何億円って製作費をドブに捨てることになっちゃう。だから『2』『3』と続けて、そのうち火が付くよう展開しなきゃいけなかったということもあるよね。
1本作ってダメだったからといってやめちゃうのはもったいない。企画する人も作る人も、『面白くないものにしよう』なんて思ってる人はいないんだから、どこかしら面白いはずなんだよ。それでも失敗するのは宣伝が悪いのか、時代に合わないのか……ダメだったらなぜダメだったかを分析して、次はその作品のいいところを活かしながら展開していかなきゃ。東映アニメーションにはそういう会社であってほしいよ」
東映アニメーションは2026年に創立70周年を迎える。日本初の本格的なアニメ製作会社であり、今もトップとして走り続ける自社に、森下氏はどんな思いを抱いているだろうか。
「外から見るとうちは『ドラゴンボール』に『ONE PIECE』、『美少女戦士セーラームーン』や『プリキュア』とメジャーなものばかりやっているように見えるかもしれない。でもそうではないマイナーな作品や、コツコツと進めているものもあるんだよ。
例えば『THE FIRST SLAM DUNK』だって公開までにかなりの年数かかったんだから。『アニメ化は絶対やらない』という原作の井上雄彦先生に『やる』と言ってもらえるために、社内で作った企画を何本も没にして、パイロットフィルムをお見せして、ようやく『CGでここまでできるなら』と許可をいただいた。そんなふうに、今後もいろんなことに挑戦していく会社であってほしいね」
森下孝三(モリシタコウゾウ)
1948年7月17日生まれ、静岡県出身。1970年に東映動画(現・東映アニメーション)に入社し、演出助手を経て「キューティーハニー」「ゲッターロボ」などの演出を手がける。「聖闘士星矢」でシリーズディレクターを務め、製作途中に企画部へ異動、プロデューサーへ転身。その後「ドラゴンボール」シリーズのプロデューサーとして活躍した。2011年には「手塚治虫のブッダ-赤い砂漠よ!美しく-」で監督を務める。2022年に東映アニメーション代表取締役会長に就任。