野田サトルは「ゴールデンカムイ」アベンジャーズ、担当・大熊八甲氏が執筆の舞台裏語る
ニュースサイト・コミックナタリーの15周年記念企画「この15年に完結したマンガ総選挙」の授賞イベントが、去る1月20日に東京都内で開催。大賞作品となった「ゴールデンカムイ」の担当編集・大熊八甲氏が出席した。
イベント前日に実写映画が公開されたばかりの「ゴールデンカムイ」。イベントでは作者・野田サトルと長年タッグを組む大熊氏が、「ゴールデンカムイ」執筆の裏側や、秘密のベールに包まれている野田の人柄などについてトークした。このレポートではイベント全体の模様に加え、ファンから募った質問に対する大熊氏の回答などを、1万字超の大ボリュームでお届けする。
取材・文・撮影 / 佐藤希
ファンの支えに感謝「この賞には特別な重みを感じています」
「この15年に完結したマンガ総選挙」は、ニュースサイト・コミックナタリーの15周年を記念した企画。2008年7月1日から2023年6月30日までに連載が完結したマンガ作品を対象にしたユーザー参加型のマンガ賞で、ユーザーの投票数が多かった15作品をノミネート作品として選定し、その後、本投票により「ゴールデンカムイ」が大賞作品として選ばれた。
イベント当日は小雨がちらつき、一時は東京都内も雪予報となる冷え込みの中、抽選で選ばれたファンが参加。会場には野田が受賞記念に主人公・杉元佐一を描き下ろした色紙も展示され、撮影を希望するファンが列を作るなどして会場内の熱量を上げていく。イベント進行は「ゴールデンカムイ」ファンでもあるフリーアナウンサー・森遥香が担当。森の呼び込みにより登場した大熊氏は、ステージ上で「GOLDEN KAMUY」とロゴがプリントされたTシャツをアピールしていた。
トロフィーを受け取った大熊氏は、野田から預かった受賞コメントを読み上げる。
野田サトルの受賞コメント
ご来場の皆様、ご投票いただきました皆様、この度はとても素敵な賞をいただきまして感謝しております。
2014年に連載が始まった本作ですが、2015年にコミックス第1巻、2016年にマンガ大賞、2018年にTVアニメが放送、同年手塚治虫文化省マンガ大賞、2019年には大英博物館のキービジュアルを飾らせていただくなどたくさんの頂に登ることができました。これはひとえに支えていただいた皆様のおかげです。本当にありがとうございます。
まだ連載前、作画資料用にとても長い銃の模型を担当氏とえっちらおっちらかついで徒歩で運んだ日が、昨日のような遠い昔のような気がします。どの道のりも大変でしたが、とても楽しいものでした。命を削って狂った犬のように描いてまいりましたので、せっかくの景色をあまり覚えていませんが、楽しかったという気持ちは覚えています。
おかげさまで先日19日には実写映画が公開されました。良い出来ですので、ぜひご覧ください。
そして本日、多くの読者の皆様からいただいたこの賞は、本作の集大成だと思います。本当にありがとうございました。
ずいぶん走ってまいりましたので、ひと休みしたいところですが、もうすでに新たに狂った犬のように走り初めています。「ドッグスレッド」、こちらも僕の脳内にはすでに最高の景色が見えていますので、もしよろしければまだ伴走いただければ幸いです。
野田のコメントを大熊氏が読み終わると会場から盛大な拍手が。「せっかくの景色をあまり覚えていませんが」という野田のコメントに、“伴走者”であった大熊氏も「僕もほぼ覚えていないんです。よそ見もしたし無駄なこともしましたが、必死だったので。情報量とイベントの数が本当に多くて、刺激のインフレで脳がバカになっちゃったんだと思います」と苦笑するが、「ただ確かに面白かったのは覚えています」と補足した。
改めて今回の受賞についての感想を求められると、大熊氏は「うれしいなという気持ちがあります。この賞のとてもうれしかったことは、完結した作品に贈られるという点。さまざまな賞をいただいてきましたが、読者の皆さんの参加型ということで、この賞には特別な重みを感じています」とファンの支えに感謝する。「野田さんもインタビューでおっしゃっていたんですが、きちんと終えることができたんだという、1つの証左としていただいた評価だと思っています。きちんと完結したことでよい作品と認められたということを実感できてうれしかったです。勝ち負けではありませんが、投票してくださった皆さんの勝利です」と述べた。
“ゴールデンカムイアベンジャーズ”みたいなものが野田さん
先日コミックナタリーで公開された受賞記念インタビューにおいて、「僕が思っている以上に『ゴールデンカムイ』が愛されていたことがわかって、改めて幸せです」と述べていた野田。森から「多くの読者に愛された理由は?」と問われた大熊氏は「さまざまな要素があると思いますが、あえて重要な点を挙げるとするのであれば、野田さんの人間としての魅力かなと。マンガって作家さん自身が出るんです。どんなに丁寧に隠しても、やはり魂のかけらみたいなものが現れて、この人はこういう側面があるんだなとわかるんです。対峙している僕自身、野田さんが人間として魅力的だと思うので。そこが愛された理由なのではないかと。嘘をつけないからにじみ出た、あの方の魅力だと思います」と長い付き合いを経て感じる野田の人柄について語る。
森が「イベント前の楽屋で(『ゴールデンカムイ』は)野田先生が魂をちぎってみんなに分け与えるかのようだとおっしゃっていましたね」と明かすと、大熊氏は「アンパンマンの顔のようですね。焼いて補充して……、今ボロボロですけど」と返す。続けて森が「『ゴールデンカムイ』のキャラクターで、野田先生に近いかも?と思うキャラクターは?」と質問すると、大熊氏は頭を悩ませつつ「本当にオールスター。“ゴールデンカムイアベンジャーズ”みたいなものが野田さんなんです。知恵、狡猾、寡黙……ちょっとふざけるところもあるし、少年のような部分もある。どのキャラクターがっていうより、野田サトルは唯一って感じですね」と説明した。
受賞記念インタビューの中で、野田は自身と大熊氏の関係を「僕がめちゃくちゃ早い暴れ馬で、大熊さんは武豊」と表現している。この例えについて大熊氏は「これはかなりのリップサービスですね、武豊さんに申し訳ないです」と笑う。「確かに野田さんは名馬ですが、僕は乗せていただいて振り落とされないように必死なんです。たまに落馬しそうになるんですけど、『今、落馬しそうです』って言うとちゃんと立て直してくれますから。だから僕は、物語から脱線しないようにする、読者さんのリトマス試験紙のような存在だったと思います。読者の皆さんはそれぞれの感性があると思うんですが、(作品の感想として)僕は実に平均的な反応を返していました」と振り返る。
野田の過去作「スピナマラダ!」から「ゴールデンカムイ」を経て、最新作「ドッグスレッド」でもタッグを組み、10年を超える付き合いとなる大熊氏。森から「野田先生と対立したことはあるんでしょうか」と聞かれると、大熊氏は「ないと思います。そこは野田さんの人柄が大きいですね。こちらの意見を真摯に聞いたうえでリアクションをしてくれる方なので、衝突する理由がないんです」とコメント。先ほどの競走馬とジョッキーの例えになぞらえて、大熊氏は野田について「走り方は暴れてるんですけど、乗り心地がすごくいい。ただ、血だらけで誰も通ったことがない道を走るので、ジョッキーとしては不安ではあります。でもいい景色を見せていただきましたね」と微笑んだ。
「いいネタがあるんですよ」あの迷キャラクターの誕生秘話が明らかに
「ゴールデンカムイ」連載期間で一番印象に残っていることについて、大熊氏はある年のクリスマスイブのエピソードを挙げる。「野田さんと2人で代官山のおしゃれなレストランでご飯食べていて。雑誌の年末進行だと、その年の最終原稿が終わるのがだいたいクリスマス近くなんですよ。だから(イブとはいえ)特別な意味はないんですけど。そこで野田さんが『大熊さん、ちょっといいネタがあるんですよ。……クマを掘るんです』って言い出して、『なんですか……?』って。そうやって姉畑が生まれました」と作中屈指の迷キャラクター・姉畑支遁の誕生秘話を紹介。会場が沸く中、大熊氏は「野田さんの頭の中にはずっと構想があったと思うんですけど、外にその考えを出したのはあのときが初めてだと思います。ちょっと自分の戸惑いが出てしまいました……。『何言ってんのかな、どうかしてる』と思いましたけど、最高に面白かった。忘れがたい思い出ですね」と感慨をにじませた。
その後話題は「ゴールデンカムイ」執筆にあたって行われた数々の取材秘話へと移る。大熊氏は「取材は野田さんだけ行くこともありましたし、僕やカメラマンさんだけで行くこともありました。でもできれば一緒に行きたいですし、野田さんはとにかく現場主義なので見て描くということを徹底されていました。流氷の取材は、『ワンパンマン』作者のONEさんと行きましたね。これ落ちたら死ぬな……と思ったんですが、おふたりが落ちたらマンガ界の損失になってしまいます」とジョークを飛ばしつつ振り返る。
数ある取材経験の中でも、イギリス・ロンドンでの取材が一番過酷だったという。大英博物館で開催された展覧会「The Citi exhibition Manga」のキービジュアルを野田が担当した縁で、野田とともにロンドンに招待されたという大熊氏。現地では「野田さんって本当に真面目なので朝から晩まで無駄なく取材のスケジュールを組むんです。とにかく何かすくい取ろうという姿勢だったので、それについていくのが一番過酷でした。ヤングジャンプ編集長や一緒に行った先輩たちは『パブに行ってギネス飲もうぜ』とか言ってましたけど、僕は翌日のスケジュールがあるので一滴も飲まず。帰りの飛行機で胃が痙攣していて、リアルで『お客様の中にお医者様はいらっしゃいませんか』と言いたくなりました」とハードな日々を語る。森が「本当に野田先生ってタフですね……」と唖然としていると、大熊氏は「タフで真摯なのでそこには絶対ついて行かないといけないですし、野田さんは1人にさせられないと強く思わせてくれます」と述べた。
ファンからの質問に回答その1「これはアウトでは?」「気に入っている煽りは?」
続いて事前にファンから募った質問に大熊氏が答えるコーナーがスタート。「ゴールデンカムイ」執筆の舞台裏を聞くものや、謎だらけの野田の正体に迫るものなど多彩な質問に、大熊氏が丁寧に答えてくれた。
Q:「ゴールデンカムイ」と言えばなかなかに攻めたギャグシーンが魅力の1つだと思います。その中でもこれはアウトではないのか…と思ってしまうシーンなどありましたか? またその際はどのように相談して決めていたのですか?
大熊 野田さんはきわきわを攻める方ですが、人を傷付けるのではなく楽しませることを根底に置いているので「これはアウトだな」と思うものは基本なかったと思います。文化を笑うということはないですし、結果的に傷付いてしまう人が出てしまっても、真摯な姿勢でいたいと思っています。
ギャグシーンではないのですが、僕グロ耐性がないんです……。ホラー映画は大好きなんですけど、グロシーンは痛みを想起してしまうのできついんですよね。刃物系がけっこうダメで、これは野田さんにも伝えているんですけど。以前「僕がダメってことは、たぶん10人ぐらいダメな人いると思いますよ」って言ったら、野田さんが「僕もダメなんですよ」……って。嘘つけ! 最初に「うわあ……」と感じたのは二瓶鉄造の指が落ちたところでした。そこは、お伝えしたら少しマイルドな表現にしてくださいました。耐性がない人間でも見られるグロになるよう、野田さんがバランスを取ってくださっていますね。
森 ちなみに下ネタに関しては全部OKでしたか……?
大熊 宇佐美の“精子探偵”はたびたび話題に上がりますね。衝撃を受けましたけど、あれはキャラクターの必然性にもとづいてやった笑いであり、保健体育の話でもあるかな、と(笑)。さまざまな表現に対する想定問答はあるので、もし誤解を与えてしまったらこういう意図があると丁寧にお答えできるようにしています。ギリギリのラインが独自性につながりますから。姉畑の話は……クリスマスに聞いちゃったんだからしょうがない。野田さんがすごくうれしそうに話すもんですから。
森 クリスマスプレゼントですね。
Q:大熊さんのお名前が作中に出てきそうなカッコよさで気になります。差し支えなければ、お名前の由来を教えていただきたいです。
森 単行本の巻末に毎回「スペシャルサンクス大熊八甲」と書かれているので、気になっている方も多いと思います。
大熊 「スペシャルサンクス大熊八甲」というメッセージは「スピナマラダ!」の単行本には入れていたんですが、「ゴールデンカムイ」では最初外していたんですよ。そうしたら、野田さんが絵を描いてきてくれたんです。野田さんからの「作者が絵を描いたんだから(スペシャルサンクスは)落とせないでしょ」っていうことなんだと思います。気遣いと優しさと、逃がさないぞってメッセージなのかもしれません。
森 そんな素晴らしいメッセージが。
大熊 名前の由来は僕もずっと不思議だったんですけど、上の兄弟が双子で、僕が3人目だから(名付けは)チャレンジ枠だったのかなって。父親に聞いたら「8人の兜を持つ者の長になれ」ということだそうなんですが、意味がわからなかったです。初めてお仕事する作家さんにお会いするときに、「名前だけでも覚えて帰ってください」っていうトークができるので、そういう意味では親に感謝しています。
Q:本文とともに煽り文の秀逸さや面白さも有名な「ゴールデンカムイ」ですが、大熊さんが「これはキマッた!」と思うようなものはありますか?
大熊 弁解をすると煽り文はコミックス収録時には外れるので、本来邪魔なものなんです。そもそも作品が面白いと何を言っても面白く見えるので、全然秀逸でもなんでもない。野田さんが最初に褒めてくれたのは、アシㇼパとアザラシの扉絵に「俺はアザラシ 海のパンサー 俺は泣かない 何があっても もしも俺が鳴くならば、それは別れの時だろう。」と付けた回。次のページで即落ち2コマ的にもうアザラシが鳴いているんですけども。これはほかの作家さんも褒めてくれました。
真面目なやつは、金塊が見つかった瞬間のアシㇼパさんの顔の横に、「キミのまわりに、金の滴、降る降る。」というアイヌの詩を引用したもの。野田さんも深層心理にあの詩があったと思うので、僕もそのページを読んだときに頭に浮かんでつけました。野田さんはその詩を思って描いたわけじゃないと言っていたんですけど、絶対に深層心理にあったと思う。かなりの巻数を経て、やっと本来の意味での煽りをつけられたと思います。
ファンからの質問に回答その2「加筆修正はどうやって決める?」「締め切りは守る?」
Q:単行本化の修正加筆について、野田先生は時間があればあるだけきっとやってくださると想像するのですが、ハードな週刊連載の中でどのように野田先生のパッションと時間をコントロールされていたのでしょうか。
大熊 パッションは尽きることはないのでコントロールすることはないです。なので、体調不良やコミックス作業などのスケジュール管理が大事でしたね。
森 8年間連載を行うというのはなかなかなことだと思うのですが、野田先生の睡眠時間ってどれぐらいなんでしょうか。
大熊 寝てないんじゃないかと思いますね。ずっと描いているとおっしゃっていたので申し訳ないな、と思っています。休載してもその間ずっと描いているので。昨日も「サボってないですよ。全然寝てないですから」とおっしゃるので「大丈夫です、疑ったことないですよ」と返したら、野田先生に「ああそうですよね」と言われました。
森 加筆箇所に関しては、野田先生から「ここを加筆したい」とご提案があるんですか?
大熊 そうですね。コミックス化するときに台割という全体のページをまとめた設計図みたいなものを見ながらご相談するんですけど、そのときの野田さんの第一声はいつも「今回は何ページ増やせますか?」。ページ数を増やすと原価が上がってしまうので、上がり過ぎると作品にも読者さんにも悪いのでそこのバランスの兼ね合いが必要なんですが。野田さんは許される限り、(ページを)取れるだけ取りたいけど、その分加筆の時間もかかりますし。ちなみに2月に発売される「ドッグスレッド」2巻もすごく加筆しています。
森 受賞記念インタビューでは野田先生が「ゴールデンカムイ」連載を経て、余計なコマを削ぎ落す能力が上がったとおっしゃっていました。加筆したいと思う部分は、野田先生がもともと描きたいと思っていた部分ですか? それとも世に出した後に、「やっぱりこうしたい」と思った部分を加筆しているんでしょうか。
大熊 両方あると思います。雑誌は1作品18ページとレギュレーションで決まっているんですが、野田さんの中で21ページで描くことが理想だった回はコミックス化の際に増やしたいと考えたでしょうし。いざ雑誌に載って客観的に読んだときに「ここはこうすればよかったな」って反省会が始まるそうで、雑誌に載ってから最終的な理想形が見えてくるときがあるそうなので、そういうところを加筆したくなるんだと思います。完璧なものを世に残したいと思っていらっしゃるので。
森 ちなみに野田先生は締め切りまでギリギリ粘るタイプなんでしょうか。もし遅れそうなときには大熊さんはどのように声をかけますか?
大熊 常にギリギリなんですけど、時間はきちんと守ってくださっています。(進行の)予測を立てたときにあんまりずれないので、そこは本当にプロだなと思いますね。僕が声をかけるのは、具体的にどれぐらい待てるかとか、どのぐらいの原稿なら出せるのか、というロジックのことですね。プレッシャーをかける意味ではないんですが、「何時までは待てます、ここを過ぎると印刷所でこういう作業が発生します」とか。そういうことを話すと野田さんも理解してくださるので。「がんばってください!」とか根性論の声がけを求める方ではないです。
森 野田先生はとても頭の回転が早い方という印象です。
大熊 早いと思います。無駄な会話もあまりしない方だと思います。したくないわけではないでしょうけど。
森 先ほど楽屋で、ロンドンの取材中にガイドさんが話してくださることが全部野田先生の知っていることばかりだったので、取材を切り上げたというエピソードをお聞きしました。
大熊 ロンドンでジャック・ザ・リッパーに関する取材ができるぞということになって、ツアーを組んだときですね。ガイドさんが観光客向けに説明してくださるんですけど、野田さんは勤勉なので事前にご自身で調べて知っていたことばかりだった。だから野田さんは「今回はお金を払ってもう終わりにしましょう」と切り上げたんです。ガイドさんも「あ、もう終わり? じゃあお酒でも飲みに行こうかな」って帰られました。そのあとタクシーの運転手さんを捕まえて、「ジャック・ザ・リッパーの事件現場を回ってください」って独自のツアーを作り始めたんです。すごい方ですよ、本当に。
Q:「『ゴールデンカムイ』は、北海道を舞台にした男たちによる愛憎渦巻く作品」と野田サトル先生はおっしゃっていましたが、大熊さんから見て、「一番愛憎渦巻いていた」と感じる人物やシーンはありますか?
大熊 一番というとすごく難しい。愛憎の相乗効果っていうか、関係が1対1ではなく、あちこち絡み合っているので渦巻のような愛憎の相関図ですよね。野田さんは「みんな愛憎まみれですよ、ははは」って言ってます。
個人としては鶴見と月島の関係性は好きですが、自己投影が入ってる可能性があります。連載が終わった後に野田さんからサプライズで色紙をもらったんですけど、そこに描いてあったのが月島でした。だから野田先生が鶴見なのかなって。月島は何も言わないでしっかり仕事をするところが好きですね。編集者もいろいろいて、自分で看板立てて仕事する人もいますが、僕はどっちかっていうと影で暗躍してるほうが好きです。
Q:これまでにも「ゴールデンカムイ」そして野田サトル先生は数々の賞を受賞なさっており、大熊さんが式に参列なさってきたかと存じますが特に印象に残っている賞などはありますでしょうか?
大熊 どの賞も思い出深い。授賞式などに伺うと、いつもスペシャルな光景だなと毎回思いました。野田さんは奥ゆかしい方で本当に表に出ないので、僕が代わりに出席することが多いんです。結果何が起きたかというと、公の場に出ると「野田先生とよく似てますね」と声をかけられてしまう。「野田サトル」とネットで検索すると授賞式の僕の写真が出たりするので……(笑)。
森 (笑)。ほかに授賞式関連のエピソードがありますか?
大熊 いたずら好きな方なんで、実は舞台袖で見ていることもあります。本日は体調と原稿作業の兼ね合いで来られなかったんですが。野田さん本人はトークもうまいですし、サービス精神がある人なんですが、作品と自分を混同してほしくないから表に出ないという美学があるんです。最近は実写映画が公開される関係でたくさんインタビューに答える機会があるので、少し疲れていらっしゃるから申し訳ないんですが……。
ファンからの質問に回答その3「サービスしすぎでは?」「白石スタンプはなぜ生まれた?」
Q:読者へのサービス精神溢れる野田先生に、「これはサービスしすぎなんじゃないか」と思ったことはありますか?
大熊 まあ、谷垣でしょうね……。ちょっと毛づくろいしすぎ、膨らませすぎ、かわいがりすぎ、コメント量多すぎかな、と。個人的にはサービスはあればあるほどいいと思ってるんですが、谷垣に関しては激しく愛の偏りを感じています。実写映画での谷垣役の大谷亮平さんにお会いしたときも「もっとムチムチになってくださいね」と言ってて。大谷さんも「けっこう筋トレしたんですけどね」っておっしゃっていました。いい関係性だと思います。
森 ほかにも本編では樺太編のバーニャのようなサービスシーンがありましたね。
大熊 カメラ目線でしたね。美少女ものの作品などでよくある、キャラクターたちが決めポーズで正面を向いているっていうシーン。野田さんあれ見ると、「みんな正面向いてるじゃん」って笑っちゃうらしくて一度やってみたかったんですって。
森 ラッコ鍋の回もサービスシーンだったんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう?
大熊 あれはちゃんと野田さんの中で必然性があって。ラッコ鍋を通じてアイヌ文化を描けるし、バッタの蝗害から逃れてアシㇼパとインカラマッを2人にしないといけないし。2人のシリアスな空気と、ラッコ鍋シーンで緩急もできる。「これは絶対出すべきなんです! 意味があるんですよ!」って僕はなんにも否定してないのに野田さんが熱弁するので、僕は「わかってますよー」って言いました。
森 谷垣が写真館で撮る写真もサービスシーンなのかなと思いました。
大熊 (野田の)愛情ゆえのことなので、皆さん谷垣をかわいがってやってください。
Q:ゴールデンカムイにはさまざまな名シーンがありますが、野田先生が描き上げた原稿を大熊さんが受け取って初めて目にしたときに、最も衝撃を受けたシーン(話数)はどこでしたか?
大熊 1話から衝撃はありました。野田さん動物を描くのがめちゃめちゃうまかったので。前作のテーマがアイスホッケーだったので、動きのあるシーンを描けるのはわかっていたんですけど、絵柄って実は読者さんへの入り口の広さなんです。うまい下手じゃなくて、入り口をどれだけ広くできるか。入り口が狭いから悪いわけではありませんが、野田さんは「スピナマラダ!」より入り口を広くするという意識のもとで「ゴールデンカムイ」を描いてきたというのは、1話ですぐわかりました。動物を描くのはすごく難しいですから、参考用に狩猟小説を渡しておいてなんですが、こんな引き出しもあったんですねと驚きました。
Q:毎回白石の台詞に顔面スタンプがあったのが本当にツボで大好きでした。(もはやフキダシを食う回もあって大好きです。)あれが生まれたきっかけとか印象があれば大熊さんにぜひお伺いしたいです!
大熊 野田さんはデータ原稿なので、あの白石のスタンプは最初は間違いかなと思ったんですよ。「なんですかこれ、絵が残ってますけど」って。僕のそのリアクションが面白かったらしく、野田さんが「よかった」と判断したので、それ以降よく使われるようになりました。
森 白石の顔はグッズ化もされましたね。
大熊 (グッズ制作は)序盤は白石のあの顔が助けてくれて、後半は谷垣が助けてくれました。
<h2ファンからの質問に回答その4「鶴見のタイトルコール回の裏話は?」「スピンオフで描いてほしいエピソードは?」
Q:鶴見中尉のセリフ「いわば…ゴールデンカムイか」でのタイトル回収のシーンについて、読者を意識したサービスだと言われていたことがとても印象に残っています。そのほかのシーンにもそういうサービスはあるのでしょうか?
大熊 鶴見のタイトルコール回ですよね。タイトルコール回ってすごく気持ちが上がるんですよね。この作品がどうして生まれたのかっていうことを客観的に見られるので、1作品につき1回ぐらい許されている感覚があります。あのシーンの必然性はかなり前から考えられていました。天然痘でアイヌの方が亡くなられたときに天然痘も悪いカムイとして捉えることがあって、つまり神っていいことばかりではなく、自然現象などの過酷さも例えているんです。じゃあ金塊も人を狂わす力があるから、カムイということでいいんじゃないかというのはけっこう前に話し合っていました。だからあの場で、アシㇼパに対する答弁および事実として鶴見に言わせる必然性があるので、読者サービス回およびカムイというものの考え方を示すために描いています。あのセリフはロシア語でもいいんじゃないかという意見もあったんですが、さすがにわからないので……。ほかのサービス回を挙げるとなると、そうじゃない回を探すのが難しいくらいインフレが起きていて大変でしたね。
森 読者の受け取り方を考えて執筆されているんでしょうか。
大熊 まず一番大事なのは自分が面白いと思うものを描くこと。野田先生をシェフと例えるなら素材を自分で用意して「どう調理すればこの素材のよさに同意してもらえるか」という打ち合わせを、最初に味見人である僕とやる、というイメージですかね。野田さんが面白いと思うものという大前提のもと、皆さんの趣味嗜好とか美味しいと思うもの、反応がよかったものに対して力を割いていくっていうサービスをしています。
Q:作中に登場する食べ物は、実際に食べていますか? 何が美味しかったですか?
大熊 法律上食べられないものもあったんですが、野田さんとアナグマの脳みそを食べたときはけっこう面白かったですね。シェフが骨まで出して解説してくださいました。門前仲町のお店なんですがそこには完結までずっとコミックスを送り続けていました。あと(新宿にあるアイヌ料理の店の)ハルコロさんには本当にお世話になりましたね。
森 お店の方々も「ゴールデンカムイ」を好きでいてくださっていますよね。
大熊 読んでいただけただけで、とてもありがたいです。お客さんが増えたと言ってくださったこともありました。
森 ちなみに一番美味しかったものはなんでしょう?
大熊 ハルコロさんで食べられるもので、名前を失念してしまったんですが胃腸薬にもなる木の実。黄檗(おうばく)という木の皮を漬けたお酒も美味しかったです。
Q:今後、もしゴールデンカムイのスピンオフマンガがあるとしたら、作中で「それはまた別のお話…」で締めくくられていたエピソードの中でどれが大熊さんの最も推したい(野田先生に描いてもらいたい)エピソードでしょうか?
大熊 そうですね……。主人公2人の物語は本当にきれいに終わったので、個人的な感情で言えば脇役とか端役のキャラクターのその後が見たいですね。岩息舞治のロシア編とか夏太郎とか、アシㇼパに失礼なことを言って杉元にのどをつぶされた男の話とか。野田さんの中でまだ描くべきものがあったと思えば、いつか時が来れば見られるかもしれません。どうなるかはわかりませんが。
ファンからの質問に回答その4「“和風闇鍋ウエスタン”というコピーはどうやって生まれた?」「野田サトルの正体は?」
Q:実写映画化やアニメ化について、原作サイドとしての関わり方等について聞いてみたいです。
大熊 餅は餅屋じゃないですけど、まずプロを信頼するのが大事じゃないかなと思っています。野田さんもプロを尊重する方で、そのうえでプロだからって投げっぱなしにするのではなく、「原作はこういう意図でこういうところを大切にしています」という思いをきちんと齟齬なく伝えることがすごく大事かなと。アニメも映画も、制作においてマンガより人数とお金と時間がものすごくかかるんです。マンガって少数ロットで作るすごく純粋な媒体なので。多くの方と作ると伝言ゲームが生まれて、齟齬が発生しやすいんですね。なのでそのときに作者が大切にしてきたことを伝えて、進行していくことが重要になるのかなと。アニメも実写も、原作側の話を聞くことを大切にしてくれたなと思います。
森 実写映画の制作も、野田先生がかなり見守っていたそうですね。
大熊 野田さんは脚本をきちんと見ていましたね。撮影ってやっぱり現場でのアレンジも入りますし、スケジュールの都合で編集部が野田さんは(見学に)行けなかった部分はあるんですけど。しっかり責任を持って同じチームとして関わらせていただきました。
森 映画に登場するクマには野田先生も太鼓判を推していました。
大熊 みんなも不安視してたクマですが、いいクマになったと思います。
Q:「和風闇鍋ウエスタン」という言葉すごく好きです! この言葉はいつ頃使い始めたのですか。また、どなたが考えられたのですか。
大熊 マンガ大賞をいただいた後ぐらいに考えた気がします。絵柄もそうですが宣伝コピーって作品の入り口を広げていく力があるんです。「この作品ってどう面白いの?」「こういうところがいいよ」と“売り”ポイントは、作品と読者さんの間の共通言語になるんですよ。じゃあ「ゴールデンカムイ」は、と思ったときにすごく難しくて。シェフの腕がよすぎるし、一流の素材が揃い過ぎて何が売りかわからなくなってしまったんです。じゃあいっそ全部乗せてしまおうと。マカロニウエスタンと呼ばれる、エンタテインメントとして西部劇が流行った70年代のピカレスクロマンやアンチヒーローものが野田さんは好きなので、ウエスタンはそこから。でも「西部劇じゃないじゃん!」というご指摘はあると思うので、マカロニのところを和風闇鍋と変えたら、思いのほかハマったので多用するようになりました。
森 読者だとしっくりくるフレーズです。闇鍋という表現がうまいですよね。
大熊 ちょっと野田さんに失礼かもしれないと思ったんですが、野田さんはそういうのも許容してくれるので。
Q:作品の中に登場した場所(北海道、東北、樺太などの外国)で特に思い入れがある所はありますか?また描かれなかったけど検討した場所はありますか? ぜひそれらの場所を自転車で巡ってみたいです。
大熊 自転車! 野田さんなら「やれるもんならやってみろ」って言うかもしれません(笑)
森 (笑)。思い入れのある場所はありますか?
大熊 どの地域も思い入れはありますね。描きたかったけど描けなかった、もしくは、描く構想があった可能性があるのは、ロシアのほうとかでしょうか。あっちにいくのは野田さんの中で構想があった可能性があります。あと意外と沖縄の方面もアイヌの方と仲良かったらしく、日本海側で交易があったそうなんですよ。沖縄にまつわるエピソードがあっても面白かったかもしれないですね。おすすめだと網走監獄とか小樽とか。挙げるときりがないですね。どこも楽しいです。
森 ぜひ自転車で!
大熊 過酷なツアーを! アップアップしてきてください。
Q:秘密のベールに包まれた野田先生の正体を教えてください。見た目、性格、チャームポイント、弱点、必殺技、座右の銘、なんでもいいです!
大熊 じゃあ座右の銘を。「神は細部に宿る」と、「描くということは見るということ」とおっしゃっていました。「神は細部に宿る」は作品を見ていただければわかると思うんですけど、僕が驚かされるほど細かい仕掛けがあるんですよ。例えば、親分と姫のエピソードで最後の夕焼け空の雲がハートだったり。誰にも気づかれなくて、かかった労力に見合わなかったらどうするんですかって、意地悪なことを聞いてみたことあるんですけど、「誰かが気づいてくれたらそれで十分です」と。読者さんとの信頼関係ですよね。見返りを求めているんじゃなくて、丁寧にしっかり自分を見てくれる誰かに向けてやっているんだなと。「描くということは見るということ」というのは「手癖で描いてはいけない」「ちゃんと本物の対象物を捉えて見て描く。すると上達するし、作品に対して得るものがあるよ」と常々おっしゃっています。それが一番効率的だ、と。
森 読者としては納得の説得力ですね。
大熊 「スピナマラダ!」の頃は全然お金なかったですけど、そのときからけっこう高額な作画資料を買ってましたね。仕事場に行ったらめちゃくちゃ置いてありました。当時は新人さんなので、それほど広い家には住めないですが、家の中にギチギチと。今でもやっぱり本物を見て自分で写真を撮るのが一番いいそうです。
これからの野田ワールドもぜひよろしくお願いします
1時間たっぷりかけて「ゴールデンカムイ」の裏話が語られた本イベント。終盤には、来場者の中から3人に野田のサイン入り単行本が贈られる抽選会も行われた。最後に観客への挨拶を求められた大熊氏は「本当に何度言っても言い足りないぐらい、ありがとうございますとお伝えしたいです」と改めて感謝を口にする。「皆さんのお声や、作品に対して思っていただいていることが野田さんの糧になっていることは肌で感じています。寡黙な方ですが、『楽しかった』とか『面白かった』とか、『たまにはこうしたほうがいいんじゃないか』みたいなお声が、すべて野田さんのエネルギーになっています。今回の賞のコンセプトも含めて皆さんと作っていただいた『ゴールデンカムイ』だと思います」と述べ、現在連載中の「ドッグスレッド」にも言及。「また北海道で会えます! すごく取材して野田さんが完璧に作っているし、愛憎渦巻くスポ根マンガになっています。先の構想を聞きましたが、やっぱり面白い。損はさせないと担当編集は思っています。これからの野田ワールドもぜひよろしくお願いします!」と力強く語り、温かい拍手に包まれながらイベントを締めくくった。

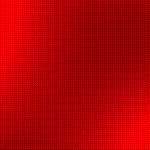


 クロ
クロ
